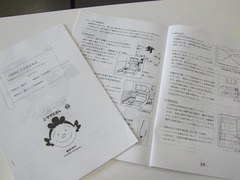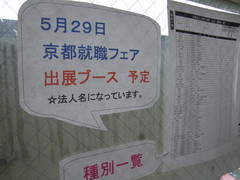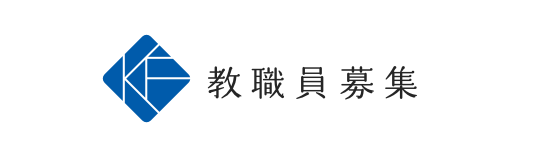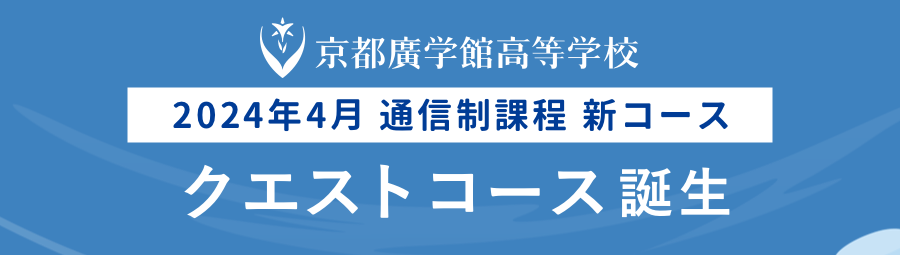2011年 6月30日スクールライフ
スクールライフ
新聞紙ディスク
1期生が来ました
☆ボーリング大会☆
2011年 6月8日スクールライフ
昨日は毎年恒例となった、ボーリング大会を行いました。
小倉駅近くのKYO-ICHI BOWL宇治にて、2学年合同での大イベントです!!
↑ 京都福祉杯の優勝トロフィー!!誰の手に? ↑実行委員長の安田君の挨拶
↑豪華景品の数々♪やっぱ皆自転車狙い? ↑ 校長先生の挨拶です。
写真をいっぱい撮ったので、沢山載せます!!
まだまだ載せきれないのですが。。。
とにかく、皆楽しそうでしたよ!初めて喋る人と喋ったりして、1年生と2年生の交流も深められているようです。








2ゲーム終了して、いよいよ順位の発表です。
チーム戦と個人戦、どちらにも商品がでます。
上位入賞者だけではなく、飛び賞にも豪華賞品が!
チーム表彰!!




個人表彰!!






今年も無事に終了!
なかなか盛り上がったのではないでしょうか!!
このボーリング大会は、レクリエーション授業の一環として行っています。
なので、学生の中から実行委員を選出し、実行委員が中心となって、学生達で進行していきます。
景品の準備、挨拶や司会、どうしたらイベントを盛り上げられるのか、それを学んでもらうための企画。
まだまだ課題は残ると思いますが、今年学んだ事を来年に生かしてもらいたいですね。
皆さん、お疲れさまでした~
最後に集合写真です♪(写真は2年生全体と実行委員)


とうとう完成!!
介護の基本
行ってきました!!
スクールライフ
2年生の5名が母校である、南京都高校2年生福祉・保育コースの授業へおじゃましてきました。
授業では、京都福祉の2年生がベッドメイキング、移動の介助、認知症の方とのコミュニケーションをし、高校生のみなさんに間違い探しをしていただきました。
高校生のみなさんも積極的に発言していただき、今回の交流はとても良いものになったのではないでしょうか。


左の写真は、ベッドメイキングをしています。
右は利用者さんに声掛けをしています。
それぞれ間違いに気づきますか?
答えは・・・
左→膝を床についていることです。
右→利用者さんとお話しする時、上らか見ています。本当は目線の高さを合わします。
写真ではわかりませんが、認知症の方とお話をしていて、
例えば、「ご飯を食べたのに食べていない」と言われても
食べたましたよ! と、否定をしてはいけません。
高校時代にお世話になっていた先生方が、卒業生の技術を見られるのは2年ぶり。
みんなの成長ぶりにとてもびっくりされていました!!
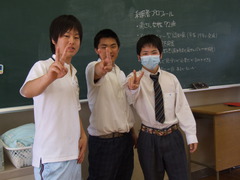
宝探し☆
就職ガイダンス
卒業生が続々と!
2011年 5月19日スクールライフ
ゴールデンウィーク明けから、卒業生が続々と遊びに来てくれています!
中には、地元大分から来てくれた人もっ!!!
恩師である齋藤先生と職場での事を話しています。
この4月から地元大分へ戻り、働きだした彼女。
毎日慌ただしいこともあってか、なんだかほっそり☆☆綺麗になっていました!
仕事はまだまだ大変な事もあるようですが、やっぱり「楽しい!!」と言っていました。
「さんきゅー!」が口癖の利用者さんに癒されているんだとか♪
卒業生のこういう姿に会うと、本当に嬉しいです。
京都まではなかなか遠いですが、また遊びに来てほしいです!!
そしてこちらは↓5年前に卒業した四辻くん。
勤務して5年、今は老人保健施設にて勤務しています。
とても逞しくなった気がします。
しかも!2児の父となった四辻くん、カワイイお子さんを連れて来てくれました。
仕事に家庭に、充実した日々を送っている様子が見られました。
本当にみんなの成長が本当に頼もしいです!
京都福祉専門学校はいつまでも、皆さんの母校です。
いつでも遊びに来て下さいね~!