2016年 10月13日お知らせ
先日行われました、第1回入学試験には出願いただきありがとうございました![]()
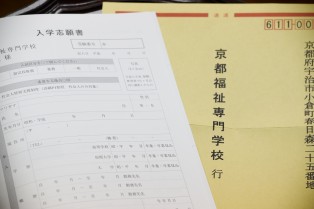 さて、只今、第2回入学試験の願書募集中です
さて、只今、第2回入学試験の願書募集中です![]()
求められる職業『介護福祉士』を京都福祉で
目指しませんか?!
一次募集第2回入学試験
10月22日(土) 出願期限:10/21(金)
入学試験についての詳細はこちらをご覧ください
願書などのご請求はこちらからお願いします
ご不明な点は、お気軽にお問合わせ下さい![]()
![]() 0774-21-7088
0774-21-7088
教育・社会福祉専門課程 介護福祉科
職業実践専門課程
2016年 10月13日お知らせ
先日行われました、第1回入学試験には出願いただきありがとうございました![]()
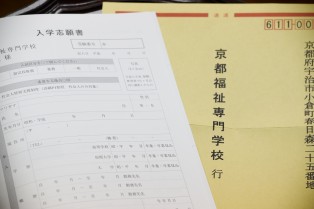 さて、只今、第2回入学試験の願書募集中です
さて、只今、第2回入学試験の願書募集中です![]()
求められる職業『介護福祉士』を京都福祉で
目指しませんか?!
一次募集第2回入学試験
10月22日(土) 出願期限:10/21(金)
入学試験についての詳細はこちらをご覧ください
願書などのご請求はこちらからお願いします
ご不明な点は、お気軽にお問合わせ下さい![]()
![]() 0774-21-7088
0774-21-7088
2016年 9月20日お知らせ
いよいよ本日9月20日より
平成29年度生.入学願書の受け付けが始まりました!!
一次募集第1回目の入試は10月8日(土)
出願書類は10月7日(金)必着でお願いします。
※9月中に提出された出願書類などは、本校にて保管し、10月3日(月)に開封し受付いたします。
入試についてのご質問は入試係までお気軽にご連絡ください。![]() 0774-21-7088
0774-21-7088
お知らせ
台風16号が近畿地方に接近しています![]()
現在、京都・大阪に、大雨・洪水警報が発令されました。
本日1年生の実習は中止とします。外出することなく自宅待機してください。
今後の台風情報には十分に注意し、担当教員・施設担当者さまの指示に基づき行動してください。
2年生は休業中ですが、くれぐれも外出を控えるようにしてください。
2016年 9月15日お知らせ
本校は京都で唯一の福祉分野.職業実践専門課程の学校です![]() 詳細はコチラから
詳細はコチラから

職業実践専門課程で取り組んでいる非常に重要なことのひとつが、本日午後より開催されました![]()
それは、教育課程編成委員会と学校関係者評価委員会です。
福祉分野の外部委員の先生方も参加し、京都福祉の状況やカリキュラムなどについて激しい議論が行われました。
カリキュラム編成や学校運営など、今後の教育活動に反映させたいと思います。
ありがとうございました![]()
内容や報告書などは、適時ホームページなどで報告させて頂きます。是非ご覧ください。
2016年 9月7日お知らせ
超高齢社会に突入している日本は、介護福祉士の人員不足が大きな社会問題となっています。
社会人、大学・短大生のみなさんを応援します!!
国や本校独自の支援制度利用し「介護福祉士」(国家資格)を目指しましよう!!
入試制度による支援
【社会人入試制度】
1年次前期授業料の一部7万円を免除
※本校入学時に、高等学校卒業後2年以上を経過した者。
【社会人特別支援制度】
1年次前期授業料の一部10万円を免除
※社会人入試受験者で、1年以上医療・福祉の職に就いた経験を有する者。又は関連資格を持つ者。
社会人特別制度について
教育訓練給付制度
労働者や離職者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、
支払った費用の一部を支給する雇用保険の給付制度です。
本校の介護福祉科は専門実践教育訓練指定講座です。
【専門実践教育訓練給付金】
最大96万円の給付が受けられます。
【教育訓練支援給付金】
専門実践教育訓練の受給資格を持ち45歳未満の離職者は訓練期間中、雇用保険、
基本手当の日額の半額程度を2カ月ごとに支給されます。
※支給には一定の条件を満たした社会人のみが対象となり、住居所を管轄する
ハローワークの支給申請が必要です。
※支給条件等の詳細についてはお近くのハローワークにお問い合わせください。
厚生労働省「教育訓練給付制度について」
ハローワーク「専門実践教育訓練の給付金のご案内」