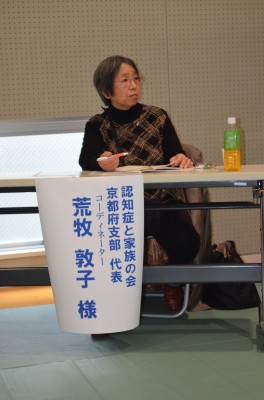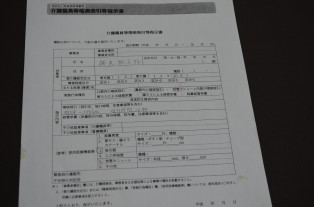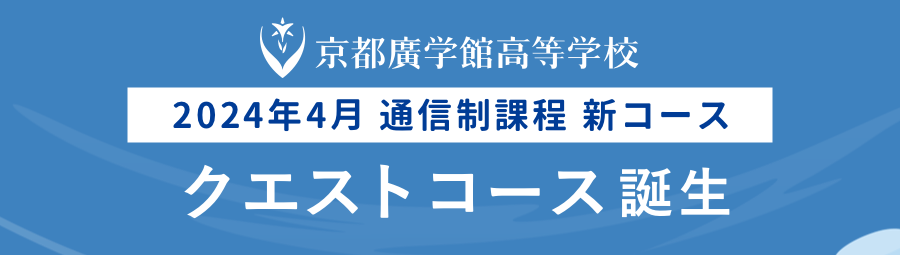2015年 11月6日
11月6日(金)生活支援技術 ~清拭~
入浴やシャワーは清潔援助として欠かすことはできませんが、利用者さんによってはエネルギーの消耗や身体の負担が大きくなります。しかし清拭はベットの上で安全に行うことができます。




タオルで拭くことで清拭効果はもちろんマッサージ効果により血行もよくなります。この時間はプライバシーに配慮して、利用者さんにリラックスしてもらうための会話と皮膚や身体の観察を忘れてはいけません。






友人同士交互にタオルの温度や拭く強さに試行錯誤!拭かれたあとの気化熱が意外と寒いのにビックリ!!介助を受ける立場にならないとわからない経験をたくさんしました。
2015年 11月5日
11月5日(木)認知症の理解
1年生の認知症の理解は一般社団法人愛生会 介護老人保健施設おおやけの里 介護士長の辻智典先生が今年から担当されています。

2015年現在、戦後生まれの団塊の世代が65歳、10年後には75歳になられ、この10年間で独居高齢者と認知症高齢者が倍増すると言われています。このような社会でこそ、介護福祉士は高齢者の日常生活を支援する関わりを通じて認知症を防ぎ、症状を改善する役割が求められます。


辻先生は言葉や数字では理論づけしづらい「暗黙知」と容易な「形式知」の2つの知識を挙げ、日常支援から利用者さんの少しの異変から大きな病気を見抜く介護福祉士や、号泣するご子息の剥離骨折を育児経験から気が付かれた奥様を例に「暗黙知」をわかりやすく説明されました。認知症ケアには治療だけでなく介護福祉士としての理論づけられた基礎知識の上に「暗黙知」を積み上げる事の大切さを授業で講義されていました。
お知らせ
Welカムfare特別講演①
開校20周年記念講演「老人を地域で生かすケア」というテーマでNPO法人「みんなの家」代表の奥田俊夫さんにお越しいただきました。奥田さんは40歳で京都福祉専門学校に入学され介護福祉士取得後、静岡県で一番の高齢化率を誇る西伊豆町で通所介護施設「みんなの家」を創設されました。高齢者の多くが農業と漁業に従事され、近所付き合いが残るこの地で奥田さんは高齢者の社会参加と活動、維持と回復に重点を置く活動の一環で、お年寄りの苦労話を聞き“人生紙芝居”をつくり誕生日にご本人や地元小学校で発表された後にプレゼントされています。戦争体験など“マイナスの人生”を“伝える使命”に変える事が高齢者にとって生きがいとなります。今年は戦後70年、戦争経験者の多くは亡くなり要介護化しています。戦争は若くて強い有能な人を重んじ、老人や障がい者を切り捨ててきたので福祉の対極に位置します。老人介護の現場こそ、戦争体験の伝承を担うべきでは?と奥田さんは講演を締め括られました。

Welカムfare特別講演②
認知症サポーター講座が行われました。講師として「認知症の人と家族の会」から代表の荒牧敦子先生と新保博先生「北宇治地域包括支援センター」代表の森下 良亮先生にお越しいただきました。認知症とは超高齢社会へ突き進む日本にとって深刻な問題で、85歳以上であれば4人に1人症例があると言われています。 決して自分だけは大丈夫というものではありません。実際に認知症を患うとご本人は「何かおかしいな」と不安と同時に苦しみ悲しみを感じられています。そこ へ家族や地域の人間が認知症を理解して優しく包み込み、誰もがさりげなく「人間杖」になって援助する社会が望まれます。この日はパネラーとして新保先生が 受講者の様々な疑問や質問に答えていただき中身の濃い講演会になりました。特に介護福祉士は人としての尊厳を大切にして更に理解を深める必要があります。 今日の講演の終わりに受講者全員が認知症サポーターの証であるオレンジリングをいただきました。

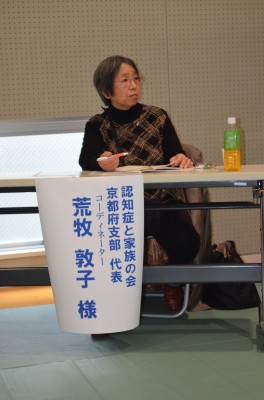


Welカムfare~老人食体験~
本校の生活支援技術の調理実習担当、講師の石田二三代先生と学生スタッフが参加者と一緒に老人食の調理・食事体験が行われました。献立は①ご飯②豆腐入り ハンバーグきのこソース③キャベツと人参のサラダ④カボチャのスープ⑤フルーツヨーグルトでした。ハンバーグには豆腐とひじきが入っていてとてもヘルシー で、御爺さんとお孫さんの参加者にも美味しく召し上がっていただけました。♪もちろん、ご飯はスキムミルク入りの栄養満点ご飯です。




2015年 10月30日お知らせ
本校では、10月31日(土)、『Welカムfare』という感謝祭を開催します。

この祭は、「日頃お世話になっている近隣の方や施設の方々へ感謝の気持ちを形にする」とう主旨で開催します。学生が主体となり本番ぎりぎりまで作業を進めてきました。




《日 時 》 2015年10月31日(土)10:00~15:00
《内容》
模擬店(おもてなしカフェ 綿菓子 菓子パン ※老人食体験)
卒業生20周年記念講演 認知症サポーター講座
ボッチャ(障害者スポーツ)昭和の展示と遊び コンサート
※数量限定。
《場所》 京都福祉専門学校(宇治市小倉町春日森25番地)
2015年 10月29日
10月29日(木)生活支援技術
本日3回目の調理実習が行われました。




献立は

①ご飯
②煮魚
③キャベツとにんじんのゴマ酢和え
④さつま芋と玉ねぎの味噌汁
⑤ブラマンジェのフルーツソース
今回の①ご飯には若い人に比べて乳製品を摂取することに慣れておられない高齢者に対して違和感なく食べてもらう工夫としてスキムミルクを混ぜています。見た目や素材の味はもちろん、乳製品を意識させないレシピは石田先生の神髄ですね。
2015年 10月26日お知らせ
10月26日(月)1、2年合同人権学習
「ヘン」な人と共に~積極的な平和の実現~というテーマで日本キリスト教団上鳥羽教会牧師の月下星志さんにお越しいただきました。

日本社会は同じ考えを持つ者と行動することに安心感を持ち、人と違う意見を述べ「ヘン」と思われることに不安を感じ、「ヘン」と思った人との間に壁をつくる傾向にあります。
人種や国籍の違い、障害者やホームレスの方々を知ろうとせずに壁をつくるのではなく、月下さんは“バザールカフェ”で在日外国人などの“社会的マイノリティ”と呼ばれる方々に雇用を提供したり、京都夜回りというホームレスの方々に声掛け活動をされています。
月下さんは「ホームレス?ハウスレス?」を例に講義を進められました。簡易宿泊所の斡旋を受けても、以前のコミュニティーが懐かしくなり元の場所に舞い戻るホームレス。家や仕事があっても悩んだ末に自死されるサラリーマン。両者が必要だったのは人から関心を持たれ、何でも話せる安らぎのある場所“ハウス”ではなく“ホーム”だったのです。あなたも「ヘン」という壁を取っ払うところからはじめませんか?
2015年 10月23日
10月23日(金)生活支援技術~入浴介助~1年生は全員水着に着替えて入浴体験(男女別々)を行いました。

介護福祉士として利用者さんの健康状態を常に考え、プライバシーを配慮して安全で楽しい入浴環境をつくるのは当たり前ですが、利用者さんにとっては遠慮や羞恥心が付きまといます。利用者さんの目線に立って友人と交互に特殊入浴装置やシャワー介助を体験をしました。


入浴装置を体験した学生は「お湯に浸かると浮力が生じ自身の体が不安定になり怖かった。お湯が引くと体にかけられていたタオルが重くのしかかり思った以上に体に負担が大きい」と感じてました。
今日の体験をいかして立派な介護福祉士になってくださいね!
2015年 10月22日
10月22日(木)生活支援技術
講師の石田二三代先生の生活支援技術は高齢者にやさしい食事づくりも今日で2回目です。


お米を30分前から水に浸して、食材の筋や余分なモノを取り除く下 処理の甲斐があり美味しく出来上がりました。



献立は

①全粥
②とりのささみあんかけ
③にんじんのたらこ和え
④かき卵汁です。
お知らせ
10月22日(木)医療的ケア~気管カニューレ内部吸引~
2年生の医療的ケアは気管カニューレ内部吸引の実技試験が行われました。



呼吸困難の利用者さんは負担を和らげるために気管の前を開窓して気管カニューレを装着されています。気管カニューレの吸引は今までの口腔内・鼻腔内吸引以上に感染症のリスクが高く、機器や吸引チューブのメンテナンスも洗浄水ではなく、滅菌精製水を使います。

もし誤って奥まで吸引すると神経を傷つけしまう危険性があるので医師からチューブ挿入の長さや、吸引時間などしっかり指示を受けて行うことが大切です。

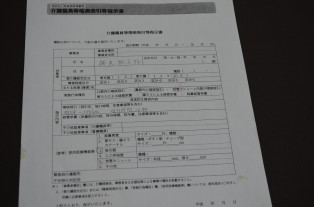
実技試験を何度もすることで吸引や観察が苦手だった学生もスムーズに行えるようになり、自ら間違いに気付きリカバーする成長した姿に試験官の先生は感動していました。